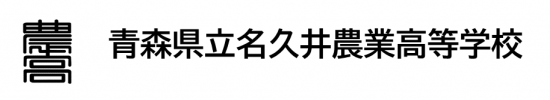令和7年度の課題研究
令和7年度 本校の課題研究の取り組み
生物生産科
野 菜 班:生物刺激剤の活用
南部太ねぎ60年の歴史をこえて地域とともに育む未来への飛躍
糠塚きゅうりに関する研究
アレチウリに関する研究
野菜のコンテナ栽培に関する研究
果 樹 班:モモの栽培~みどりの食糧システム戦略CO₂の削減~
絵入りリンゴの品質向上について
イチジクの生育と環境適応について
猛暑が果樹に与える影響~JGAP認証園での取り組み~
農村文化班:里地里山活性化プロジェクト ~里山植物の飲食料品開発を中心に~
栽培環境班:肥料の地域内自給と土と作物の強健化に関する研究
環 境 班:耐暑性、耐乾性試験
気化熱を利用した耐暑性技術の開発
水耕栽培におけるアオコの発生を抑制する技術開発
除草剤の泡散布システムの開発
アクアバイオポニックスの開発
乾燥地での食料生産技術の開発
養液栽培班:ミドリムシ入り培養液で品質向上
水耕イチゴのインテリア~お部屋を飾るグリーンファーム~
ユーグレナの培養と水耕野菜の栽培~二酸化炭素の吸収~
資源循環班:おがくずの有効活用について~時短炭焼きガマ制作編~
“ホッとする”空間作りのお手伝い
抜粋研究
農村文化班【里地里山活性化プロジェクト ~里山植物の飲食料品開発を中心に~】
長年にわたる人と自然の関わりで作り出されてきた里地里山は、昭和30年代からの生活スタイル・人口減少・自然環境の劇的な変化により、限界集落・消滅集落の発生や自然環境の荒廃が急速に進み、生物多様性や農村文化の伝承などが深刻な問題となっている。そこで「食文化」を視点とした里山植物を用いた飲食料品を開発することによって、里地里山を活性化させていくことを考えた。
栽培環境班【肥料自給に関する研究】
野草:コンフリーから肥料をつくり、肥料の地域内自給を目指す。コンフリーは繊維が少なく、栄養分が豊富であること、繁殖力が旺盛で地域に溢れている点が素材の選定理由である。液体肥料化を目指す中で、加工や保存の方法に試行錯誤している。製造した肥料を使った栽培試験も行っている。
養液栽培班【ミドリムシ入り培養液で品質向上】【水耕イチゴのインテリア~お部屋を飾るグリーンファーム~】
【ユーグレナの培養と水耕野菜の栽培~二酸化炭素の吸収~】
①ユーグレナと水耕野菜のCO2吸収量の比較をしながら、気象変動に具体的な対策となりうるものを研究する。また、水耕栽培と養殖を掛け合わせたアクアポニックス。私たちは水その魚をユーグレナにして培養しようと研究している。
②水耕イチゴ生産に取り組んでいるが、施設初期費用の問題で普及は進んでいない。水耕野菜はクリーンなイメージから、カフェ・レストランで活用されている事例から、インテリアとして活用する方法を研究している。
野菜班
【糠塚きゅうりに関する研究】
「糠塚(ぬかづか)きゅうり」は、青森県八戸市糠塚地区を中心に南部地方で栽培されてきた伝統野菜です。子実はうすい緑色で、太く、約500gの重さがあり、イボが黒く、独特の苦みを持ちます。昭和30年代まで広く栽培されてきたが、栽培の難しさや保存がしにくいことから生産農家が激減し、食生活の変化から食べる機会も減少してきました。そこで、糠塚きゅうりの特徴と問題点を確認し、栽培技術を改良することで生産量を向上させ、消費量や認知度が増加することで地域活性化を図りたいと考え研究を行っています。
【アレチウリに関する研究】
「アレチウリ」とよばれる「特定外来生物」だということを知りました。「特定外来生物」は外来生物のうち、「外来生物法(特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律)」により、自然環境や人の生命・身体、農作物などに被害を与える、または被害を与える恐れのある生きものとして指定された生きもののことです。生態系や人の生命・身体、農林水産業へ影響を与えると問題視されています。これらの特定外来生物は、飼育、栽培、生きたままの運搬など法律で原則禁止されています。作物栽培では、難防除雑草や外来雑草、特に「特定外来生物」は近年急速に問題化されており、その適切な防除方法が除草剤の使用量や環境負荷低減のために最も重要であると考えられます。そこで、私たちは、この「アレチウリ」の適切な防除方法を考えるため、アレチウリについて調査し、アレチウリの分布図を作成、アレチウリの適切な防除について検討しています。今後も日本各地で問題になっている「特定外来生物」について「アレチウリ」だけでなく他の動植物の被害についても検討していきたいです。
【野菜のコンテナ栽培に関する研究】
家庭での栽培の入門として「コンテナ栽培」があり、プランターやコンテナを用いた野菜の栽培方法が考えられます。ベランダなどのスペースで気軽に育てることができますが、コンテナ栽培をしたあとの土の廃棄が問題となります。そこで、長期間自家栽培ができるようなコンテナ栽培を確立したいと考え研究をはじめました。さまざまな植付け方法を検討し、循環できる栽培方法確立を目指し、栽培試験を繰り返しています。今後も、コンテナの土を廃棄せずにリサイクルできる作付け方法の確立のために、作物の組み合わせを考えたいです。これからも長期間自家栽培ができるようなコンテナ栽培方法の確立を目指し、研究をすすめて行きたいと思います。